愛知県名古屋市の名古屋港湾会館において、「第15回京都大学国際シンポジウム:生物多様性と動物園・水族館 -生き物からのメッセージ-」を開催しました。本シンポジウムは、本学の独創的な学術研究を世界に向けて発進し、国際的に開かれた大学としての活動を積極的に展開していくことを目的としており、京都大学教育研究振興財団の後援を得て、平成12年度以来、世界各地で開催しているものです。今回のシンポジウムは、そのテーマから、研究者や学生、動物園・水族館関係者だけでなく、一般からも多くの参加者があり、二日間で8カ国から延べ約480人が訪れる活発なものとなりました。
シンポジウム初日は、野生動物研究センターの幸島司郎 教授の挨拶に始まり、「第1部:自然生息地での研究と保全」としてブラジルのアマゾンカワイルカやインドのアジアゾウをはじめとする世界各地の研究を紹介しました。午後には、本学を代表して藤井信孝 理事・副学長が挨拶を行い、シンポジウムのテーマである生物多様性に対して、大学と動物園・水族館が協力しながら貢献していくことの重要性を述べました。続いて、山田雅雄 名古屋市副市長の挨拶があり、直前の講演についてのコメントや名古屋市の紹介など親しみやすい内容で、会場は和やかな雰囲気に包まれました。その後行ったポスターセッションは、2室用意した会場がどちらも大変な盛況となり、発表者と参加者が熱心に質疑応答をする場面があちこちで見られました。
同日夕刻に名古屋港水族館の黒潮水槽前で行ったレセプションでは、マイワシの群れが泳ぐ幻想的な雰囲気の中、動物園・水族館関係者と研究者・学生が歓談し、交流を深めました。
二日目には「第2部:動物園水族館での研究・保全・教育」として、アメリカやオーストラリアの動物園・水族館の取り組みや研究協力についての発表があり、参加者も熱心に聞き入りました。シンポジウムの最後には祖一誠 名古屋港水族館長、小林弘志 名古屋市東山動物園長から、生物多様性に対するよりよい貢献を目指して、シンポジウム提言が発表されました。
動物園・水族館と大学等の研究機関との協力や研究が他国に比べて遅れていると言われる日本において、本シンポジウムはお互いの活動を知り、協力体制を強めていく上での画期的な機会となりました。これを機に、環境教育や研究、生き物の保全の分野でより活発な協力体制が構築されていくことが期待されます。
 左から挨拶をする幸島教授、藤井理事・副学長、椹木哲夫理事補 | |
 ポスターセッションの様子 |  レセプションの様子 |
 満員の会場の様子 |  二日目の発表の様子(1) |
 二日目の発表の様子(2) | 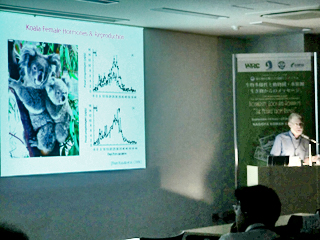 二日目の発表の様子(3) |

