百周年時計台記念館において、「第13回京都大学国際シンポジウム:学術研究における映像実践の最前線」を開催しました。京都大学国際シンポジウムは、本学が誇る独創的な学術研究を世界に語りかけ、国際的に開かれた大学としての活動を積極的に展開していくために、平成12年度以来毎年、世界各地で開催しているものです。今回のシンポジウムは、京都大学教育研究振興財団の後援を得て、内外の研究者や学生のみならず学界外からも多数の方々が集まり、大きな盛り上がりを見せました。
シンポジウム1日目は、松本紘 総長の映像上映による挨拶で開幕しました。続いて、本シンポジウム実行委員長の地域研究統合情報センター 田中耕司 教授から趣旨説明の後、学術情報メディアセンター 土佐尚子 教授によるオープニング上映を行いました。
その後セッションI「海洋生物がみせる海」、セッションII「脳科学と映像」、セッションIII「宇宙物理学と映像」を行いました。
同日夕方に行ったレセプションは、吉川潔 理事・副学長の挨拶、西村周三 理事・副学長の乾杯の発声でスタートしました。今回のシンポジウムでの発表者の専門分野は幅が広く、普段お互いに顔を合わせることのない研究者同士の親交の場となりました。
2日目は、セッションIV「映像がとらえる野生動物」、セッションV「映像メディアとエスノグラフィー」、セッションVI「映像メディアとアクティヴィズム」を行いました。
3日目は、セッションVII「ヴィジュアル・イメージと社会-親密圏と公共圏の再編成に向けて-」、セッションVIII「ヴィジュアル・イメージと物語」、セッションIX「カルチュラル・コンピューティング-文化・無意識・ソフトウェアの創造力」を行いました。まとめとして、田中教授の総合司会でセッション担当者や若手研究者を交えた総合討論を実施しました。活発な意見交換が展開され、熱気のうちに幕を閉じました。
学術研究における映像にかかわる実践に注目した、今回のこのような分野横断的な学際シンポジウムは、世界的にも類をみないものでした。今後、映像を通じた新たな学術領域の開拓の第一歩となることが期待されます。
 松本総長の映像上映による挨拶 |  セッションVIの様子 |
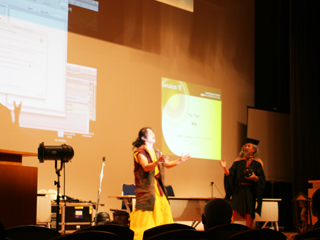 実演を交えた発表 |  総合討論の様子 |
 左から田中教授、森純一 国際交流推進機構長、吉川理事・副学長 | |

