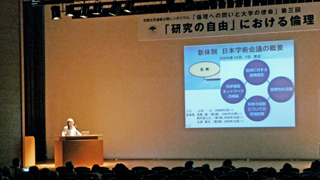百周年時計台記念館百周年記念ホールにて、京都大学連続公開シンポジウム 「倫理への問いと大学の使命」(第3回) ~「研究の自由」における倫理~を開催しました。
今回のシンポジウムは、研究の自由への倫理的制約の議論や、研究成果や論文の捏造、研究資金の流用、研究上の差別等の問題が生じ、研究者自身の倫理が問い直されようとしている昨今において、「研究の自由」のもつ意義と価値を討議する趣旨で開催されたもので、学外からの一般参加者を含め120名が参加しました。
東山紘久 理事・副学長の開会挨拶の後、基調講演では、「科学者の倫理と行動規範」と題して、入倉孝次郎 名誉教授から、平成18年に日本学術会議から声明が出された「科学者の行動規範について」の作成経緯や、科学者の不正行為の分析状況、アンケートの調査状況について説明があり、その現状と問題点について話がありました。
パネル講演では、「生命倫理への挑戦は研究の自由を拡大するか?」と題して、柳田充弘 生命科学研究科特任教授が、生命科学研究の歴史とそれに伴う同分野に対する倫理の考え方の変遷について説明があり、21世紀において個人的な情報や価値が倫理の上でより一層の鍵となることなどが語られました。その次に「工学研究者倫理の領界」と題して、井手亜里 工学研究科教授からカラシニコフ氏やモルデハイ・バヌヌ氏の倫理の領界(Territory)を例に倫理(Ethics)と良心(Conscience)の境界及びその重複部分について語られました。また「研究はだれのものか」と題して、横山美夏法学研究科教授からは、社会科学上や法律学上での研究の自由やその社会的影響について話がありました。
最後の講演者全員によるパネル討論では、それぞれの専門分野の立場から活発な意見交換が繰り広げられました。最後に、コーディネーターの位田隆一 公共政策大学院教授が、「研究の自由」について考えることは、科学や科学者とは何か、科学と社会の関わりをどのように考えるかに繋がるものである、研究成果がもたらす光と影的な側面も踏まえて科学者自身がその責任を考え、社会の側もそれらを注視する必要がある、その全体の中で倫理やその保障としての「研究の自由」を再認識する必要がある、とまとめました。