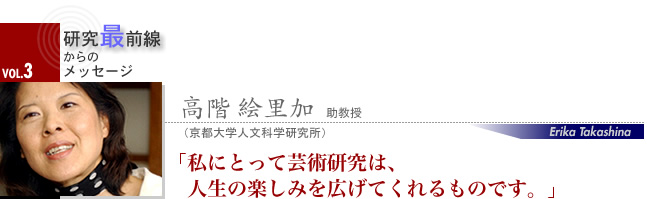
高階 絵里加(たかしな えりか)先生の研究領域は、19世紀を中心とするヨーロッパおよび日本美術史、なかでも明治期の日本美術を中心としています。この時期は西洋から「美術(Fine Art)」というまったく新しい概念が移入された時期でもあり、また少々乱暴な言い方をすれば、西洋がルネサンス以降300~400年かけて歩んできた歴史を20年ぐらいの間に経験したともいえる、非常にドラスチックな変革を経験した時期です。したがって当時の芸術家たちは主題や技法を求めてもがき、試行錯誤を繰り返しました。先生はこの時期の日本美術界の足跡を検証する中から、将来を展望しようとするユニークな研究を展開されています。また一方では、美術を真に活かす=広く人々に鑑賞してもらうために、全国のシンポジウムやワークショップに出かけ、研究成果をわかりやすく語る活動をされています。今回は、高階先生の芸術研究に傾ける情熱、芸術鑑賞の楽しみなどについて、お話をうかがいました。
「明治の美術はきちんとした歴史になっていないので、研究対象とするにはまだ早いという雰囲気がありました。」
日本美術史の分野では、仏像や浮世絵など江戸時代以前のものについての研究は長い伝統があり今も盛んだが、高階先生の専門である明治期の日本美術については、それまでにも個々のすぐれた研究者はいたが、本格的に組織的な研究が始まったのは1980年代からで、まだ20年ほどしか経っていない。先生自身も大学院の修士課程までは、新古典主義のアングルや印象派のドガなどを中心にした19世紀のフランス美術を主に研究されていた。「明治の美術はきちんとした歴史になっていないので、研究対象とするにはまだ早いという雰囲気がありましたね」。
しかしヨーロッパの研究者から「あなたは西洋の美術を研究しているそうだが、日本の美術はどうなっているのか?」と問われて、ドガやアングルと同時代の日本の美術についてほとんど何も知らないことに気づかされ、愕然とすると同時に、明治期の美術に興味を抱くきっかけとなった。また同じ頃、明治美術の研究会が立ち上げられている。参加してみると、今まで見たこともないような絵と次々に出会い、自分の国のものなのに知らなかった世界に足を踏み入れる面白さを覚えることになる。
そして1993年、高階先生は山本芳翠という画家の展覧会を見て、その不思議な絵の数々にショックを受けた。それは完全に西洋の油絵の技法で、「浦島」「十二支」といった日本的な主題を描いており、そのときにはグロテスクで不気味な感じさえしたという。この今まで見たこともないような「日本風油絵」に衝撃を受け、高階先生の研究が本格化するのである。2000年には、明治美術において日本がどのように西洋を受け入れ、交流したかをまとめた『異界の海―芳翠・清輝・天心における西洋―』(三好企画)を出版、日本の美術批評界に一石を投じる書として話題になった。
「明治期の日本の美術は、 みんなが試行錯誤して走り回っているような面白さがありますね。」

高階先生に明治期の美術の魅力について尋ねると、「みんなが試行錯誤して走り回っているような面白さ」という答えが返ってきた。そもそも西洋の「アート」に対応する「芸術・美術」という言葉自体、明治の初年代に移入されたもので、日本において画家は絵師=職人だった。西洋画が入ってきたとき、その風景画や人物画を見て、ものを正確に描けるという技術的側面に最初は重きが置かれ、当初は実用的なものとして受け入れられたようだ。しかし明治10年代以降、西洋に留学する画家たちが、彼の地ではそれらが「芸術」として、その国の誇りにもなっているという実態を目の当たりにし、美術を実用のものから芸術へと脱皮させようという動きが起こってくる。それは西洋に並ぼうとする日本の国策ともあいまって、日本独自の歴史や文化を世界に発信しようという考えにもつながる。そして前述の山本芳翠のように、日本神話の世界や日本的な習俗などに主題を求めた絵画が数多く描かれるわけだ。「当時の芸術家は外的な要因や内的な欲求など、いろんなものが錯綜して、ずいぶん不思議な絵も描かれたのですが、でもすごく生き生きとしていた時代なのではないかな、と思います。」
さらに高階先生は最近の論考で次のように記している。「現在でも国際的に活躍する日本人アーティストほど、西欧の技術を吸収した上で、多様な『日本的なるもの』を意識しつつ制作してきた。それはいまや、アニメーション映画のような大衆芸術の領域にまで広がっている。今後、日本文化の海外への発信がどのような方向に向かってゆくのかを見極めるためにも、明治中期の『日本画』『洋画』の枠組みでは捉えきれない、いわば『第三の道』の歩みを検証し、近代日本美術史の見直しを図ろうと考えている。」美術史とは、単なる歴史研究にとどまらないという宣言である。
「もともと言葉ではない美術作品を、言葉に置き換えて語っていくこと。そうすることで、過去に人間が生きながら遺していったものと対話しているのです。」

高階先生のお話を聞いていると、美術史という分野は、科学的でありしかも、ある意味とても人間臭い学問だと感じられ、興味をそそられる。では先生と美術史との出会いはどうだったのだろう。
幼い頃から海外での生活が多かった先生は、中学の半分以上をフランスで過ごし、イタリアの教会などにも家族でよく出かけた。そのとき教会の祭壇画の図柄がそれぞれ何かを象徴していること(目玉を持っている女性=目をくり抜かれた殉教者の聖女ルチリア、車を持っている女性=車裂きに遭った殉教者の聖女カタリナ、ペリカン=親鳥が胸をつついてその血で雛を養うところから「犠牲」を意味するetc.)などを、父(高階 秀爾 氏・現大原美術館長)から教えられ、「絵って、こんなふうに言葉で語れるんだ。面白いな」と思ったのが、この世界への入り口だったという。
絵には、それが生まれてきた必然性というものがあるはずだ、と先生は言う。画家の内面から湧き起こる欲求に加え、画家を取り巻く環境や社会背景が、画家とその作品に何らかの影響を与えているかもしれない。そういったところまで含めて探求することで、芸術鑑賞の世界がぐんと広がってくる。
「絵が生きていくためには、 その時代に生きている人たちを必要としているのです。」

そういう芸術鑑賞の入り口を人々に示し、広げることが、美術史家の大きな役割だと先生は考えておられる。「絵というのは生きているのです、その時代時代に。ほこりをかぶって人々から忘れられていたら、それは絵もきちんと生きていないのであって、そういうものを本当に生きている状態にしてあげるのが、研究者の使命だと思います」と熱っぽく語る。人文研に来られた当時、顧みられないままになっていた須田 剋太の絵があった。それを修復し、その絵の前でミニコンサートを開いたことがある。「そのとき、本当に『絵が喜んでいる』と実感したんです」。こんなエピソードを紹介しながら、先生はそのときを思い出したように、とても華やいだ表情を見せてくれた。また先生は、そういう幅広い見地から美術を研究するには、人文研という場所は非常に居心地がよいとも言う。「芸術研究というのはそれだけで閉じているものではなくて、まず歴史的な知識が必要ですし、文学や音楽とも関わりがありますし、なんといっても人間のことすべてに関わっていると思うので、同じ建物にさまざまな分野の専門家がいて、気軽に尋ねたりできるのは、本当に幸せなことです。」人文科学研究所そして今後の大きなテーマのひとつとして、美術史を歴史という側面から語るだけではなく、個々の作品に即しながら、ひとつの文化のあり方として語っていくことを挙げられた。「そのためには、人文研での共同研究というものが、将来は大きな助けになってくるのではないかと思っています。」芸術を愛し、芸術研究をとことん楽しもうという高階先生の、今後の研究からは目が離せない。
取材日:2005/12/7
Profile
19世紀を中心とするヨーロッパおよび日本美術史、なかでも明治期の日本美術を研究されている高階 絵里加 先生。1988年に東京大学文学部を卒業後、99年同大学院人文社会系研究科博士課程を修了文学博士号を取得、2000年に京都大学人文科学研究所に助教授として招かれました。以後、明治期の日本美術界の足跡を検証する中から、将来を展望しようとするユニークな研究を展開されています。また一方では、全国のシンポジウムやワークショップに出かけ、研究成果をわかりやすく語ることで、芸術鑑賞の裾野を広げようという活動もされています。今回は、高階先生の芸術研究に傾ける情熱、芸術鑑賞の楽しみなどについて、お話をうかがいます。

