iGEM(The international Genetically Engineered Machine competition)とは、マサチューセッツ工科大学(MIT)が主催するシンセティック・バイオロジー(Synthetic biology)の国際大会です。通常の学会と異なり、チームごとのコンペティションという形をとっており、2009年度は世界各国から112チームが参加する過去最大の規模となりました。プロジェクトの決定から文献調査、テーマの組み立て、実際の実験やシミュレーション、資料の作成と英語での発表までを「学部学生が」主体となって行うというユニークな大会です。参加者は、あらかじめ大会本部から送られてくる遺伝子の「標準パーツ」や、チーム独自に設計した遺伝子を組み合わせることにより、新たな機能を持った細胞をつくります。そのアイデアの独創性や新規性、社会的意義に加え、実験で達成した成果をMITで口頭・ポスター発表し、その出来映えを競います。
iGEM京都大学チームは2008年度に結成しました。メンバーは様々な専攻の学部学生を主体とし、加えて修士院生とアドバイザーから構成されています。初参加の昨年度は、テーマの独創性は群を抜いていましたが、残念ながら入賞を逃しました。「今年こそは」と意気込んだ2009年は、さらにユニークなプロジェクトを2つ(Time Bomb とCells in cells)立ち上げ、主に夏休みの期間を利用して遂行し、10月31日から11月2日までMITで行われた本大会に参加して銀賞(silver award)を受賞しました。
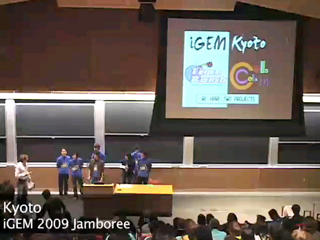 iGEM大会での京都大学チーム口頭プレゼンテーションの様子 |  MITでのiGEM京都大学チームの記念写真 |
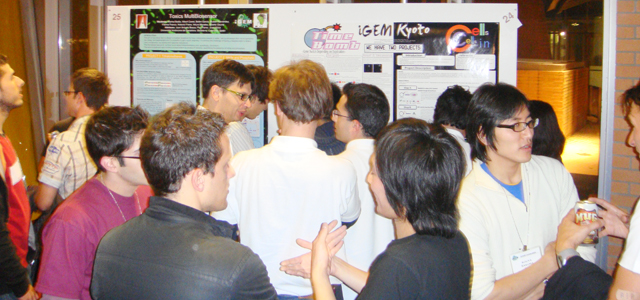 ポスター発表での様子 | |
以下にその概要を簡単に説明します。
(1) Time Bomb
~Gene Switch Depending on Duplication(GSDD)分裂回数依存的タンパク質発現機構~
「Time Bomb」は、文字通り「細胞時限爆弾」ですが、危険なものではなく、バクテリアなどの細胞を産業利用するために、「あらかじめ決められた時間後に不要となった細胞を除去する」ことを目指した研究です。

たとえば、ある遺伝子組み換えをした大腸菌を人体や生態系で利用することを考えた場合、その大腸菌により、用いた環境中で予期せぬ事態が生じるということが常に危惧されます。
そこで、何らかの人為的な目的を持って遺伝子組み換えされた生物が、環境中で必要以上に増殖、生存しないように、細胞の分裂回数に依存して、細胞死をひきおこすというシステムの構築を目指しました。
(2) Cells in cells
~細胞内共生系の再構築による細胞の本質へのアプローチ~
「細胞とは何か?」また、人工的に作った「細胞みたいなもの」がどれくらい環境に依存せず、どのような機能をもっていれば細胞と呼べるのでしょうか?
この質問に自力で答えるために、今年の京都大学チームは、ミトコンドリアに着目しました。ミトコンドリアは通常細胞とみなされませんが、細胞内共生説によると、元来独立した一つの細胞であったと考えられます。現在ミトコンドリアは必要なたんぱく質のほとんどを、共生している外部環境である細胞のたんぱく質に頼っています。そこで、ミトコンドリアが外部のたんぱく質を取り込むために必要なシステムを人工の脂質膜に再構築し、その脂質膜が生きた細胞内でミトコンドリアのように機能すれば、それこそが人工細胞モデルになるのではないのかと考えました。すなわち、人工的な細胞内共生システムを創ることで、細胞構築原理の理解に迫ることを目指しました。
これら二つのテーマを掲げて参加した京都大学チームは、MITで行われた本大会初日に、英語での口頭プレゼンテーションを200名近くの聴衆を前に行いました。さらに2時間におよぶポスター発表での数多くの質疑応答(すべて英語)の後、審査を経て銀賞を獲得することができました。昨年、全く賞を獲得できなかった無念を考えると大きな躍進でした。プロジェクトの斬新さ・新規性に対する聴衆の評価は高く、多くの人から「面白かった」「非常にユニークだ」などと評価していただきました。参加した学生からは、「良い経験になった」「大変な時期もあったがやり遂げてよかった」「来年も是非参加したい」といった声が挙がっています(コンペの合間にはダンスパーティなども開催され、参加各国のチームとの交流も楽しめる大会でした)。それぞれの学生にとって非常に貴重な体験であり、将来にこの経験が多分に生かされることとなると考えられます。
一方、優勝のCambridge大学チームをはじめ、決勝に残った6チームをみると、高度に組織化され、主催者側の要求を十分満たした上で、質の高い実験成果とプレゼンテーション能力を披露していました。京都大学チームが来年勝つための課題も浮き彫りになりました。
参加のご案内
iGEMは、Synthetic biologyという分野をモデルとして、学部生が研究現場の醍醐味を実際に経験し、その成果を自ら国際的に発信できる貴重な機会です。その活動は実験のみならず、チームWebサイトの作製、シミュレーションなど幅広い活動内容があり、文化系理科系問わずどのような学部の方にも活躍の場がありますので、皆様の参加をお待ちしております。 是非、以下のアドレスまでご連絡ください。この活動に賛同、または直接ご参加いただける教員の方のご連絡もお待ちしております。
iGEMkyotoチーム
連絡先: iGEM.Kyoto*gmail.com (*を@に変えてください)
ホームページ: http://igemkyoto.com/
iGEM 2009 京都大学チームメンバー
学生
学部
畠山昭一(理学部 物理 4)
田伏洋介(理学部 化学 4)
林瑛理(理学部 生物 4)
永易陽一(理学部 数学 4)
鹿島誠(理学部 生物 3)
多田雅斗(理学部 化学 3)
日比野絵美(薬学部 3)
宮澤悠(総合人間学部 3)
佐久間航也(理学部 2)
高森翔(理学部 2)
志甫谷渉(理学部 2)
高嶋梨菜(理学部 1)
修士院生
早瀬元(理学研究科 化学専攻無機物質化学 1)
アドバイザー
齊藤博英(生命科学研究科 助教)
野村慎一郎(物質-細胞統合システム拠点 特定研究員)
戎家美紀(医学研究科 若手研究ユニット 助教)
藤田祥彦(生命科学研究科 研究員)
賛同者
吉川研一(理学研究科長)
米原伸(生命科学研究科研究科長)
井上丹(生命科学研究科 教授)

