省エネ活動の構成
省エネ活動を効率よく推進していくためには、エネルギー消費の実態把握や省エネルギー関連情報の素早い伝達等を行う必要があることからも、大学構成員の省エネルギー体制が重要となります。結果的に省エネルギーの意識の高さや、省エネルギーに関する知識に偏りがあると、理想的な省エネルギー活動には結びつきません。
京都大学では有効な省エネルギー体制をとるため、まずエネルギーを管理する区分として、キャンパス毎に管理区分(事業所)を設定し、エネルギー管理を行っています。即ち、吉田キャンパス(北部、本部、西部、吉田南、南部、病院西、病院東)、宇治キャンパス、桂キャンパス、熊取キャンパスといったようにエネルギー管理区分を設け、それぞれキャンパス毎に省エネルギー活動を行っています。
また、エネルギーの消費者である部局自らが積極的な省エネ活動を推進する体制をとるために、各部局には部局長をチームリーダーとし、そのチームにエネルギー管理主任者とエネルギー管理要員をおく管理組織(省エネチーム)構成としています。
大学全体の統括や吉田キャンパスの統括として、施設活用課がその事務を担当しています。施設活用課のエネルギーマネジメント業務としては、啓発活動、管理標準の設定、省エネルギー提案、実施、部局の省エネルギー相談などを行っています。
他に省エネ法では地区毎に有資格者であるエネルギー管理士、エネルギー管理員を必要数定めており、吉田団地のエネルギー管理士、管理員は施設活用課職員が任命されています。
また、これまで無かった大学の統括エネルギーマネジメント委員会を平成18年4月より設けて担当理事(藤井 信孝)のもとに、より質の高い活動を始める予定です。
エネルギー巡視

平成17年度エネルギー巡視(法学部)
施設活用課では1回/年(※1)エネルギー巡視調査を行っています。この巡視では部局の省エネ活動の実施状況の調査、省エネに関する分析、提案、相談などを中心に行っています。
また、部局で実施している省エネ事例など、効果的な実施例があれば、他部局への照会を行っています。
(※1)規模の大きな部局については2回/年行っています。
エネルギー管理主任者会議

平成17年度エネルギー管理主任者会議
毎年行われるエネルギー管理主任者会議では、部局におられるエネルギー管理主任者の方々に省エネ法に関する知識の向上と省エネ活動に関してのスキルアップなどについて会議を行っています。
Web検針
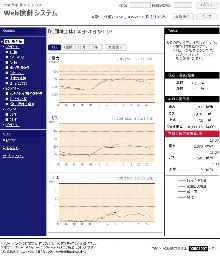
Web検針システム
現在、桂団地には各クラスターに設置してある集中検針システムと、EMセンターに設置してある中央監視装置を利用してWeb上で電気、ガス、水道の使用量をグラフ表示で閲覧できるシステムが導入されています。このシステムは使用者が各自の講座などの使用量を講座全体又は設置メーター単位でグラフ表示することができ、各自又は全体の使用量を把握することができます
他にも、温度データを同時表示させることができ、以前のデータ(過去2年分)の情報を任意にダウンロードすることもできるなど各自での省エネ分析を行うことも可能となっています。この情報を活用して、桂団地ではかなりの省エネルギーの意識が高まったと言われています。
TOPページ(ログイン画面)には桂全体、クラスター別、棟別の総使用量がグラフ化することができ学内の方であれば、桂団地の電力、ガス、水の使用量の様子を伺うことができます。
啓発活動
施設活用課では、啓発活動として色々な取組みを行っています。以下にその例を挙げます。
省エネ提案

- 省エネ巡視、エネルギー管理主任者会議などの機会に省エネルギーについての提案を行っています。
- 部局で行える省エネ工事、使用者が行える省エネ活動、省エネに関する新技術の紹介など様々な提案を行っています。
省エネポスター

啓発活動の一環として省エネポスターの制作、配布を行っています。平成17年度に制作したポスターは過去10年間の電力・ガス使用量の延びを視覚的に認識しやすい表現としました。また、省エネ活動に代表される主な活動を4種類図示しています。今後も省エネルギーに有効なポスター等の作成を行っていく予定です。
省エネラベルの貼り付け
 |  |
「電気はこまめに消しましょう。」
不在時や不使用時の照明はこまめに消すことで省エネとなります。
「ふたを閉めるだけで電力カット。便座は低温にセットしましょう。」
電気ヒーター付の便座はふたを閉め、温度は低温にセットすることでかなりの省エネとなります。
このような分かりやすく、簡単に取り付けできる啓発ラベルを作成し配布しています。照明用はスイッチ下部に取り付け、便座用はトイレットペーパーのホルダーに貼り付けるタイプのラベルを配布しています。必要な方は無料配布を行っていますので、施設活用課まで連絡ください。
新設・改修に関して
施設環境部では従来から環境に配慮した設計・施工を行っています。できるだけ快適にかつ、エネルギーを削減できるように新設・改修などでいろいろな工法、システムなどの導入検討・実施を行います。以下導入の参考例を示します。
例(電気設備関係)
- 照明器具の省エネ改修
- 高効率変圧器の採用
- 初期照度補正照明器具の一般化
- 照明回路のタイマー化による昼休みの一斉消灯
- 外灯の人感センサー・タイマーなどによる減光
- LEDランプの採用
- 入退室管理に伴う居室内電源制御
(機械設備関係)
- COPの高い空調機導入(更新)
- 空調機室外機への散水
- 省エネベルトの導入
また、施設活用課では省エネルギー対策工事の発注、相談などを行っています。
京都大学の新しい取り組みについて
ESCO事業には、削減される光熱水費をもとに設備改善(設備投資)を行う方式(シェアード・セイビングス)と、通常の改修工事のように施主が資金を用意する(ギャランティード・セイビングス)いう方式があります。
京都大学では、平成19年度より熊取キャンパスにおいてシェアード・セイビングス方式のESCO事業を、平成20年度より吉田キャンパスにおいてギャランティード・セイビングス方式のESCO事業を、それぞれ実施しております。
ひき続き、平成22年度においても実施すべく検討を進めております。
- 京都大学原子炉実験所ESCO事業
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/gyoji/esco/esco-top.html - 平成20年度・21年度京都大学吉田地区ESCO事業
http://www.kyoto-u.ac.jp/contentarea/nyusatu/nyusatu.htm

