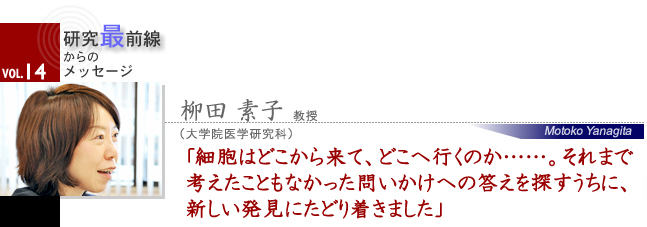
近年、腎臓病患者は年々増加し、生活習慣病の一つに数えられることもある。2011年10月に京都大学医学研究科に新設された腎臓内科学講座は、腎臓を専門に扱う単科講座であり、腎臓病研究のまさに最前線である。若くしてこの講座を率いるのは柳田素子教授。臨床に研究にと日々奮闘する教授に、腎臓病治療の現状、教授が発見した研究成果の意外なきっかけについて聞いた。
年度の途中に新たな講座が開設されるのは、異例といってよい。腎臓内科にかけられた期待と同時に、その重圧も推察される。
「うーん、プレッシャーを感じていないわけではないですが、私は楽天的な性格なんだと思うんです。どんな状況でも、「これからどうすれば講座がよくなるか、患者さんにとってはどうなるとよいのか、私たち自身もやりがいを感じて楽しくなるのか」と考えることそのものが楽しい。私たちは、いまこうして健康に生きていること自体が奇跡的なこと。そのうえで、やりがいのある仕事を任されているのですから、とても幸せなことだと思います」と笑顔でさらりと語る柳田教授だが、講座立ち上げからの日々は目の回るような忙しさだった。大学教授として研究や教育に携わるだけではなく、臨床医として診療もこなさなければならない。勝手がわからないうちは臨床業務だけで手一杯だった。1年余りが過ぎて、ようやく講座運営のペース配分が把握できてきたという。いよいよ、研究にもエネルギーを注ぐ準備が整った。
守備範囲は病院全体、患者数は無限大

腎臓の病気で多いのは、尿検査異常や腎機能の低下した状態がつづく慢性腎臓病や、それがさらに進行した慢性腎不全。慢性腎臓病患者の割合は日本の成人人口の8人に1人にのぼる。慢性腎臓病のやっかいな点は、あらゆる病気と併発しうることだ。合併症を起こしやすいとされる高血圧や糖尿病などだけでなく、まったく別の病気で来院した人が腎臓病もわずらっていることがある。
さらに、抗がん剤の投与や手術などの副作用で、院内で腎臓病を発症してしまうこともある。潜在的な患者数は無限大といっても過言ではない。病院内での感染症の発生を監視・抑制するICT(院内感染対策チーム)のように、腎臓内科には京都大学医学部附属病院全体を守備範囲とする活動が求められている。
しかし、患者の診療に携わる臨床スタッフはわずか8人。精鋭ぞろいではあるが、どうしても手が足りない。
「本院で実施した腎機能を表す血液検査、クレアチニン値が前回と比べて悪化している人を抽出し、リストアップする「Kidney Injury Surveillance System (KISS)」というシステムを医療情報部の先生方にお願いしてつくっていただきました。それを用いると、院内のどこに腎機能が悪化している方がいるかがわかります。現在は、どのような患者さんのリスクが高いのかを割り出していますが、将来的にはその患者さんが発生したところにリアルタイムに腎臓内科医がかけつけるようにしたいと思っています」。
リスクの高い腎臓病患者とは、たとえば腎臓病とがんを併発している患者のこと。現在はがん治療も進歩して、副作用が軽減され、効果も大きい抗がん剤が開発されている。しかし、抗がん剤には「腎機能が正常な場合に限る」という使用条件がつけられていることが多い。
なかでも人工透析をしている患者は、抗がん剤の血中濃度が高くなりやすいうえに透析を行うたびに血中の薬物濃度が変動し、効果が不安定になる。そのため、抗がん剤の副作用が懸念されるだけでなく、その効果についても疑問が残るが、その点を明らかにする根拠も確かではない。
「がんを発症する高齢者の方はもともと腎機能が低下している方も多く、さらにはがん治療中に腎機能が低下する方も多くおられます。腎不全の人や透析を受けている人も、そうでない方たちと同様に安全ながん治療を受けられるようにするのが、私たちの課題です。オンコロジー(治療学)とネフロロジー(腎臓病学)とをつないだオンコネフロロジーユニットを当科内に設立し、がん治療中に腎機能が悪化した方、腎不全の方のがん治療をできる限りサポートする取り組みを進めています」。
腎臓病を「治る病気」に

腎臓病治療に使われている薬の多くは、ほかの病気の治療を目的に開発された薬の流用が多く、症状を抑えることはできても、腎臓病そのものを完治させることは難しい。
いっぽう、柳田教授が講座を立ち上げたときに掲げた目標は、「腎臓病を「治る病気」に」。そのために必要な新しい薬を開発するには、病気の仕組みを把握する研究が欠かせない。
「たとえば肝炎は、以前は未知の病気で、完治させることは難しかったのです。しかし、ウィルス性の病気であることがわかってから研究が一気に進み、いまでは「治る病気」になりました。おなじように、腎臓病もこの10年で発見が相次ぎ、近々画期的な治療法や新薬の登場がありうるのではないかというブレークスルーの時期を迎えています」。
じつは、腎臓病の完治への光明となるメカニズムの一端を突き止めたのが、ほかならぬ柳田教授である。
慢性腎臓病が進行すると起こる症状は、腎臓の組織が変質してしまう「線維化」と、腎臓が機能低下して赤血球を生産させるホルモンが低下することによる「腎性貧血」だ。これまでは、いちど線維化した細胞の回復は困難というのが定説で、腎臓内のどの細胞がそのホルモンを作っているのかも知られていなかった。
柳田教授は、この二つの病態が、神経堤由来細胞というある一種類の細胞の機能不全によって引き起こされることを発見した。しかも、変性してしまった組織を再生できる可能性まで見出したのだ。この細胞の動作に狙いを絞った薬が開発されれば、腎臓病を「治す」ことに大きく近づくことができるのではないかと期待されている。
発見の端緒は、「頭のなかが耕される」異分野交流
線維化と腎性貧血のメカニズムの解明という、これからの腎臓病治療の道を大きく切り拓く発見。柳田教授がこの研究の手がかりをえたのは、なんと宗教学や数学の研究者との対話からだった。
「「腎臓にある細胞はどこから来てどこへ行くのか」と問いかけられたんです。腎臓の細胞ははじめから腎臓にあってあたりまえだと思っていましたから、そんなことは考えたこともありませんでした。でも、その一言から、この細胞が腎臓の細胞になる前はどこにあったのか、このあとどう変化するんだろうか。どのようにして病気になってしまうのか……と考えだし、そのうちに線維化のメカニズムにたどり着いたんです」。
対話の舞台は、白眉プロジェクト参加者の交流セミナーだった。白眉プロジェクトとは、さまざまな分野の優秀な若手研究者に最長5年の期間を与え、その間は自分の研究に没頭してもらうという京都大学の研究者養成プロジェクトである。柳田教授はこのプロジェクトの第1期生として異分野の研究者と議論するなかで、「頭のなかが耕されるかのような刺激」をいくども味わったという。
プロジェクトに参加した研究者の分野は、数学や宇宙物理学、昆虫学からインド仏教学や哲学まで、あらゆる範囲におよぶ。月に一度の「白眉セミナー」で医学とはまったく違う分野の話を聞くこともあれば、自分の発表に対してふだん考えもしない切り口の質問を受けることもしばしば。「目からうろこがポロポロ落ちる経験。医学は実学志向が強く、いますぐ役だつものを重視しがち。その考え方の枠を取り払っての議論は、新鮮で、衝撃的でした。できればあの環境でずっと研究していたかった」。
教師として感じる教育のすばらしさと恐ろしさ
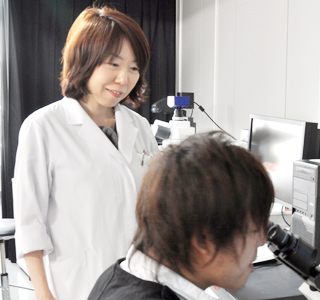
学生にとっては、日々の講義がおもしろいかつまらないかは、大問題である。柳田教授は腎臓内科学だけではなく、医学概論、分子生物学、薬理学、病理学など、腎臓に関連する基礎分野の講義も担当している。腎臓の位置すら知らなかった学生が、1時間半の講義のあとにはまるで別人のように鋭い質問を連発する。「その姿に教育のすばらしさを感じますが、学生たちに強大な影響力をもつ教師の立場の重みと、講座をもつことの責任も感じます。彼らがどれだけ、どのように伸びるかが、教師の手にかかっているのですから」。
学生のモチベーションを上げるために柳田教授が心がけているのは、基礎から臨床への連続性をもたせた授業をすること。基礎分野の授業でも、いま教えている部位の機能が破綻すると何がおきるのか、教科書にはまだ書いていないような最新の医学研究や治療法のトピックも交えて教える。基礎研究が臨床の実践にどう結びつくのかを具体例をあげて伝えると、学生は目を輝かせて講義を聴いてくれるのだという。
もちろん、研究グループのリーダーとして、大学院生7人と学部生2人の指導にもあたる。研究をうまく進めるには、メンバーどうしのコミュニケーションは重要だ。すでに研修医として患者と接したことのある大学院生が自らの経験を後輩に伝えるのはしばしばあることだ。いっぽう、講義を受けたばかりの学部生たちのほうが、最新の医学情報に関してはよく知っていることもある。大学院生と学部生とは10歳くらい年が離れていることもあるが、対等な関係で刺激しあって研究している。
京都大学をめざしたきっかけは、二人の医師と映画館通い

柳田教授が医学研究の道を志したきっかけは、二人の医師であるという。一人は子どものころの主治医の先生、もう一人は柳田教授の大伯父だ。
「小学校のころのかかりつけの先生は、とても安心感を与えてくれる方で、私は大好きでした。その先生と大伯父とは京都大学医学部の同期で、しかもライバルだったのです。大伯父は病理の研究者だったのですが、終戦直後に広島の原爆被害の調査に行って、台風による山津波に巻き込まれました。身体の弱い人だったそうで、周囲は広島行きに反対したのだそうですが、大伯父は頑として引かなかった。その医学研究者としての使命感を聞かされて育ったこともあって、この二人の母校である京都大学で医学研究をして、患者さんを救いたいなと思ったんです」。
柳田教授は高校生まで、生まれ育った神戸でのんびり過ごした。古い映画が好きで、ひまがあれば京都の映画館に通っていたという。「映画館といっても、スクリーンがクーラーの風でゆらゆら揺れるような自主上映ですが、もっぱら京都の大学生が主催している上映会が多かったですね。京都の学生文化に惹かれたのも京都大学をめざした理由の一つです」。
中高生はいま、この瞬間の感性を大切に
最後に、京都大学や医学部をめざす中高生へのメッセージをいただいた。
職業体験など、ほんらい社会に出てからすべきことの予習のようなイベントもあるが、「私は中高生が大人のまねをする必要はあまりないのではないかと思います。たった一週間や二週間、お客さんの立場で学んだところで、仕事の本質なんてつかめませんから」。
それよりももっと重要なことがある。「中高生のあいだにしか感じられないことを感じてください。たとえば、本をたくさん読んでください。小説を読んで、作者の考え方を感じ取ってほしい。中高生の感じ方は、中高生のうちだけにできる特権です」。大人になってからおなじ本を読んでも、もうあのころのようには響かない。
「医学部に入って医師をめざす人は、いろいろな人の多様な生き方、考え方を知ってください。医学部志望の人はだいたい健康で、恵まれた人たち。その世界しか知らないと、どうしても考え方が偏ってしまいます。でも、これから接することになる患者さんはさまざま。とにかく視野を拡げることが大事ですね」。

研究室で学生たちと。学生からみた柳田教授は「とにかく情熱的な先生」。先生の口癖は"What's new?"。「毎日、部屋に入ってくるたびに、2、3回は口にされます」とのこと。
取材日:2013/1/25
Profile
1969年、神戸市に生まれる。1994年に京都大学医学部を卒業。2001年に博士号取得。京都大学COE助教授、同次世代研究者育成センター「白眉プロジェクト」特定准教授をへて2011年から京都大学医学研究科教授に。白眉プロジェクトでの研究内容は「新しい国民病、慢性腎臓病の病態解明および治療法・診断法の開発」。
日本腎臓学会財団賞大島賞、日本内科学会奨励賞、日本臨床分子医学会学術奨励賞、日本血管生物医学会YIA、岡本研究奨励賞など多数の受賞歴をもつ。
日本人としては異例ながら、医学研究に貢献した科学者が推薦されるAmerican Society of Clinical Investigationのメンバーに2013年、認定された。

